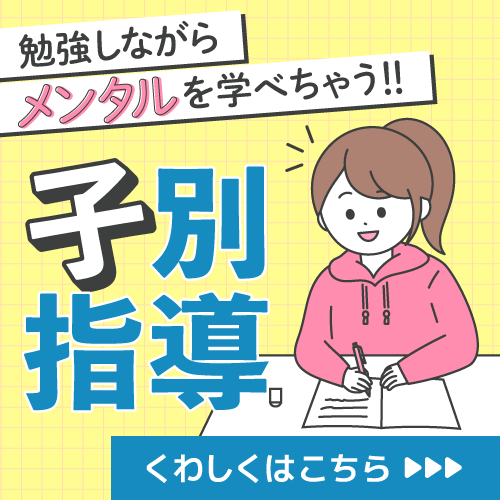「朝から何も食べてない。起きてこないから。」
「作っても食べない――もう、作る気力が出ない」
不登校の子を支える親御さんにとって、
「食事をどうするか」は、実はとても大きな悩みの一つです。
朝ごはんを用意しても食べない。
昼になっても部屋から出てこない。
声をかけても無反応。
それでも、「ちゃんと食べさせなきゃ」
と頑張っているけどこの努力ってどうなの?よく聞きます。
報われない日々が続くと、
親だってしんどい。
「もう、作らなくていいかな…」
とあきらめたくなることもあるのではないでしょうか。
今回は、「ご飯を作らない自分はダメなのか?」
と自分を責めてしまう親御さんに向けて、
少しでも心が軽くなるような視点と実例をお届けしたいと思います。
不登校を経験した子どもたちには、
ある“共通点”があると感じています。
それは、
将来に活かせる大きな可能性を秘めているということ。
私自身が元・不登校だったことに加え、
16年間多くの不登校の子どもたちを見守ってきた経験から、
本当に伝えたいことを無料のメール講座にまとめました。
気になる方は、ぜひ以下↓↓↓のリンクか画像からご覧ください。とりあえずクリック‼
不登校の子にご飯を作らないのはあり?なし?
◆ 不登校中は「食事のリズム」は崩れやすいもの
不登校になると、生活リズムがガラッと崩れます。
朝は起きられず、昼になっても布団から出てこない。
ようやく起きてきても、ジュースだけ。
夕方になってようやくスナック菓子をかじる――。
そんな「1日一食(もしくは食べない)」のような日々が続くと、
親もどう接していいかわからなくなってきます。
特に料理をしても反応がない、無視されるという状況が続くと、
作る側の心も折れていきます。

◆ 作らないのはダメ?責めなくて大丈夫です
結論から言えば、
作らない日があってもまったく問題ありません。
私自身、子どもの頃の不登校時代、母が料理に疲れ、
「今日のお昼、適当にしてね」と言ったことがありました。
大したお腹も空いていなかったのでが。
そのとき、母は外に出かけて美味しいランチを食べていたことも後で知りました。
当時は腹いせ半分、リフレッシュ半分だったのかもしれません。
でも、正直、私はそれを責める気にはなりません。
むしろ「それで良かった」と思っています。
お互い気楽に過ごせたほうが良い。
料理というのは、
作る側の心の余裕や体力を大きく消耗するものです。
中学生以降だと食事もただ口に運ぶだけではなく、
背後にある心の葛藤や不安、親子の緊張関係が大きく影響しています。
◆ 実際の親たちの声:それぞれの「ちょうどいい距離感」
ある中学2年生の母親のケース
朝昼晩と作っても、一口も食べない。
流しにそのまま残っていると、気持ちが沈む。
→思い切って“作らない日”を作ったところ、
2か月後に「おにぎり食べたい」と言われて涙が出た。
親だけでランチに出かけるようにしたケース
一緒に食べようと誘っても断られ続けていたが、
親の会で仲良くなった親だけで気晴らしに外食に行くように。
夫婦でも外食に行くように。
浮いた塾代で。
→そのうち「今度一緒に行ってみようかな」と子どもが自ら言ってきた。

◆ 筆者自身も「暇つぶしに料理してた」時期があった
私は不登校時代、自分で勝手に冷蔵庫をあさって、
お菓子や目玉焼きを作って遊んでいました。
男ながらにかわいくクッキーなどを
焼いていたことがあったのです(笑)
親が「一緒に料理しよう」と言ったわけではありません。
むしろ、放っておいてくれたからこそ自由に動けたんです。
実際、支援先の子どもたちでも
「自分でチャーハンを作ってる」
「カップ麺に野菜を足すのがマイブーム」など、
自主的に工夫する子も多くいます。
“料理は愛情”ではありますが、
“料理だけが愛情”ではありません。
◆ ずっと作らないと「見捨てられた」と思う子もいるから、メリハリが大事
とはいえ、ずっと料理しないでいると、
敏感な子は「うちの親、もう自分に関心がないのかも」と思ってしまうことも。
だからこそ、「手を抜く日」「気合を入れて作る日」のメリハリが大切です。
いつもじゃなくていい。
“ここぞ”というときに、
ふと作ってもらったご飯が、強く記憶に残るのです。
「いつもじゃないからこそ、ありがたみがある」
これは、料理に限らず、
親子関係すべてに言えることかもしれません。

◆ 無理をしない「小さな関わり」でも十分
-
一緒にコンビニに行く
-
好きなお菓子を選ばせてみる
-
「何食べたい?」と聞くだけで終わってもOK
-
自分のランチを作るついでに、「ちょっと多めに作ったよ」と声をかける
- 食事や日々の生活を楽しむ姿を子どもに見せる。というか、見せつける
こんな小さなアプローチが、
やがて大きな変化につながることもあります。
◆ 食が戻る=心が戻る兆し
ご飯を食べるようになった。
たったそれだけのことでも、実はものすごく大きな前進です。
食べることは、生きること。
「またご飯を食べたい」「作ってほしい」と思えるのは、
“誰かとつながってもいい”という心が芽生えてきた証拠です。
◆ まとめ:不登校の時にご飯を作らないのはどうなの?
不登校の子に毎回の食事を用意するのは、
本当に大変なことだと思います。
作らない日があってもいいし、
自分のために外食する日があってもいい。
料理は愛情。
でも料理だけが愛情じゃない。
ときには子ども自身が作ってみる体験も、
大切な成長。
「見捨てられた」と思わせないために、
時々“ふと作る”のが効く。
無理せず、手を抜いたり力を入れたりしながら、
家庭ごとの最適解を見つけていきましょう
食べることは、回復の兆し。
あせらず、小さな変化を見守っていきましょう
◆ 最後に
もし今、「作っても食べない…」と感じているなら、
それはあなたのせいではありません。
そして、何よりも、そんな状態でも子どもを思って悩んでいるあなたは、
もう十分に“立派”です。
大丈夫。
食は、心とともに、必ず戻ってきます。
不登校を経験した子どもたちには、
ある“共通点”があると感じています。
それは、
将来に活かせる大きな可能性を秘めているということ。
私自身が元・不登校だったことに加え、
16年間多くの不登校の子どもたちを見守ってきた経験から、
本当に伝えたいことを無料のメール講座にまとめました。
気になる方は、ぜひ以下↓↓↓のリンクか画像からご覧ください。とりあえずクリック‼
✅ 記事のまとめポイント
-
不登校の子がご飯を食べない・引きこもるのはよくあることで、特別なことではない。
-
親が料理を作る気力をなくすのも自然な反応であり、自分を責める必要はない。
-
「毎回ちゃんと作らなきゃ」という思い込みが親を追い詰めてしまう。
-
筆者の母も、腹いせに外食していた時期があり、それで良かったと思っている。
-
料理は愛情の一つの形であるが、それがすべてではない。
-
子ども自身が暇つぶしで料理を始めるケースもあり、自発性を尊重することが大切。
-
食事の提供は“常に”ではなく“メリハリ”をつけることが重要。
-
ときどき印象に残るものを作ってあげることが、子どもの記憶に強く残る「愛情表現」になる。
-
一緒にコンビニに行く、親だけでもランチに出かけるなどの小さな関わりも効果的。
-
食べるようになることは、子どもの心が開きはじめたサインである。
-
焦らず、子どもが“食べたい”と思う日を信じて待つことも大切なサポート。
-
完璧を目指すのではなく、「家庭ごとのちょうどいい形」を見つけることがゴール。