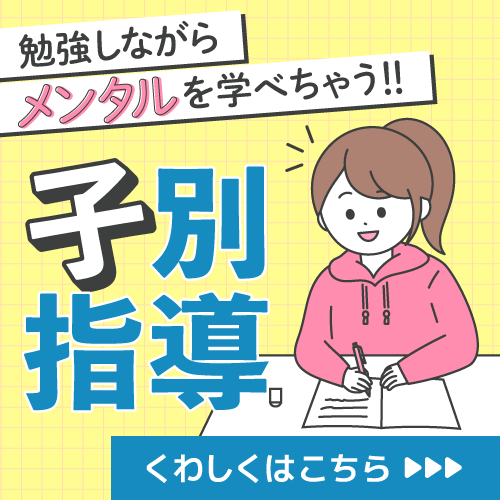🧒 はじめに:不登校な上に「勉強しない」わが子の将来が不安になり、胸がざわつくとき
お子さんが不登校になり、
さらに勉強もしなくなった時――
「このままで将来大丈夫なのだろうか?」
「勉強は最低限してほしい」
「甘やかしているだけじゃないか」
そんなふうに思い悩む保護者の方は少なくありません。
しかし、結論から言えば、「今、勉強していないこと」が
その子の人生を決定づけるわけではありません。
実際に、「不登校+勉強しなかった」状態から
有名大学に進学した子どもたちの事例もあります。
それもたくさん。
この記事では、そうしたリアルな事例を交えながら、
勉強しない子どもに対して親ができること、
心構え、そして対応策についてご紹介していきます。
不登校を経験した子どもたちには、
ある“共通点”があると感じています。
それは、
将来に活かせる大きな可能性を秘めているということ。
私自身が元・不登校だったことに加え、
16年間多くの不登校の子どもたちを見守ってきた経験から、
本当に伝えたいことを無料のメール講座にまとめました。
気になる方は、ぜひ以下↓↓↓のリンクか画像からご覧ください。とりあえずクリック‼
🌱 実例①:中学はゲーム三昧、高校生で覚醒し早稲田大学へ
ある男の子の中学時代の生活は、
ほぼ「ゲーム一色」でした。
学校にはあまり通わず、
家庭教師も週に一回ほど来てくれるだけ。
しかし、彼が家庭教師の先生に見せたのは、
ノートでもなく参考書でもなく、大好きなゲームの話。
それでも母親は「無理に勉強させなくていいです。
本人がやる気になったときで構いません」
という姿勢を貫いていました。
転機が訪れたのは高校進学後。
「勉強って思ったより面白いかも」と本人が感じ、
自発的に学び始めました。
苦手意識がなかったことが幸いし、
吸収力は抜群。
そのまま勢いに乗り、早稲田大学へ進学。
このご家庭のポイントは「学びに対する負の感情を育てなかったこと」でした。
家庭教師代を無駄にしてもニコニコしている仏のようなお母さんでした。
私にはできないなと思ったものです。

🌱 実例②:「勉強しなくてもいいよ」が導いた明治大学合格
もう一人のケースは、
母子家庭で育った女の子。
中学時代の彼女もまた、勉強に対して無関心でした。
塾には通わず、家庭教師をたまに呼ぶ程度。
あるとき、家庭教師が「今日はやる気なさそうですね」と言うと、
母親はこう言いました。
「じゃあ今日は遊ばせてあげてください。
勉強は、本人がやりたいと思ったときにやればいいので。」
結果的に、高校に進学してから、
彼女は自分で勉強の楽しさに気づき、
少しずつ自主学習を進めるように。
そして、最終的には明治大学に現役合格。
無理に「やらせる」のではなく、
「やりたいと思わせる」ことの価値がよく表れた例です。
🤔 勉強しない=甘え? ― 子どもの心理を理解する
勉強しない姿を見ると、
「甘えている」「逃げている」と感じてしまうこともあります。
でも実際、多くの不登校の子どもたちは、
心の中で葛藤しています。
🔍 子どもが勉強できない本当の理由
-
「どうせ自分には無理」という自己否定
-
「勉強=学校の延長」として拒否反応がある
-
「やっても意味がない」と感じる無力感
-
学校でのトラウマや人間関係のストレスが、学び全体への嫌悪につながっている
これらはすべて、単なる「サボり」や「甘え」ではなく、
心の叫びなのです。

👪 親ができる3つのサポート
子どもが勉強をしないとき、
親として何ができるのか。
焦りを抑え、
以下の3つを意識してみてください。
① 「ありのままで大丈夫」と伝える安心基地づくり
親が不安になると、
子どもはもっと不安になります。
まずは「ありのあなたで十分大切な存在だよ」というメッセージを、
言葉と態度で伝えましょう。
安心感が土台にあるからこそ、
学びへの意欲が芽生えます。
② 学びのきっかけは“興味”からでいい
勉強の代わりにYouTubeを見たりゲームをしたりしている時間を、
全て否定する必要はありません。
たとえば:
-
歴史ゲーム→日本史への関心
-
アニメ→声優・映像・ストーリー構成への興味
-
YouTube→発信者になってみたいという思い
好きなことを通じて「学び」につなげていくことが、
自然で強力な学習の入り口になります。
③ 将来の「選択肢の多さ」を伝える
「勉強していない=将来が終わる」と思い込んでいる子どもは少なくありません。
そんな時こそ、親からこう伝えてあげてください。
-
通信制高校、フリースクール、高卒認定など多様な進路がある
-
大学受験だって何歳からでも挑戦できる
-
大人になってから学び直す人もたくさんいる
「今すぐじゃなくていい」「まだ選べる」という安心感が、
次の一歩を後押しします。
希望やロールモデルを伝えておくことが「ある時」の力となるのです。
そうした事例は今の時代は昔と違いネット上にもたくさんありますので。

写真は上智大学。不登校から通信などを経て推薦で入る人も増えている。
💬 よくある保護者の質問とアドバイス
Q:本当に、今勉強しなくても大丈夫?
A:はい。むしろ「無理にやらせること」で学ぶ意欲を失うリスクのほうが高いです。
大切なのは「心が元気になったときに、勉強が嫌になっていないこと」です。
Q:親が何も言わなければ、子どもは変わらないのでは?
A:「言わない」のではなく、「環境を整える」ことが重要です。
子どもは親のまなざしを敏感に感じ取ります。
Q:うちは特別だから…という不安があります
A:どの家庭も、最初は「うちだけは無理かも」と感じています。
でも、子どもが“自分のタイミング”でやる気になれば、
大きく伸びる可能性はどの子にもあります。
🌸 おわりに:不登校で勉強したくない子に対してどうする?
「勉強しない=将来が危うい」と短絡的に考えがちですが、
本当の支援とは、「今、勉強させること」ではなく「今、心を回復させること」です。
やる気は、外から無理に注入するものではありません。
心が元気になると、子どもは自然と前を向きます。
子どもを信じ、情報だけはタイミングよく与えてあげる。
それが、保護者さまにできる最も大きな支援です。
不登校を経験した子どもたちには、
ある“共通点”があると感じています。
それは、
将来に活かせる大きな可能性を秘めているということ。
私自身が元・不登校だったことに加え、
16年間多くの不登校の子どもたちを見守ってきた経験から、
本当に伝えたいことを無料のメール講座にまとめました。
気になる方は、ぜひ以下↓↓↓のリンクか画像からご覧ください。とりあえずクリック‼
✅ 記事のまとめポイント
-
「不登校で勉強しない」状態=将来がダメ、とは限らない
→ 勉強を再開するタイミングは子ども自身の中にある。 -
中学時代にほとんど勉強せず、早稲田大学・明治大学に進学した実例がある
→ ゲーム中心でも、信じて見守ることで学びに目覚める時がくる。 -
保護者が「無理に勉強させない姿勢」を貫くことが、信頼と安心を育てる
→ 親の余裕が、子どもにとっての安全基地になる。 -
「勉強=学校の延長」として拒否反応を持っている子は多い
→ 一度、学びから距離を置くことで、苦手意識を薄められる。 -
“甘え”ではなく「助けてほしい」というサインとして受け取る視点が大切
-
子どもは“やらされる勉強”ではなく“やりたい学び”の方が圧倒的に伸びる
-
好きなもの(ゲーム・動画・漫画など)から学びに変換する工夫が有効
→ 好奇心を入り口にすれば、自発性が高まる。 -
勉強しない時期があっても、将来の進路は取り戻せる
→ 通信制高校、高卒認定、再受験など、道はいくらでもある。 -
親が焦ると、子どもは「自分はダメなんだ」と感じてしまう
→ 焦りや不安は一旦手放し、「今の子ども」を受け入れる姿勢を。 -
「やる気が出てから始めた方が、勉強の吸収が早い」という事実
→ 無理に詰め込むより、本人の準備が整うのを待つ方が効率的。 -
「今できていないこと」より「これからの伸びしろ」に目を向ける