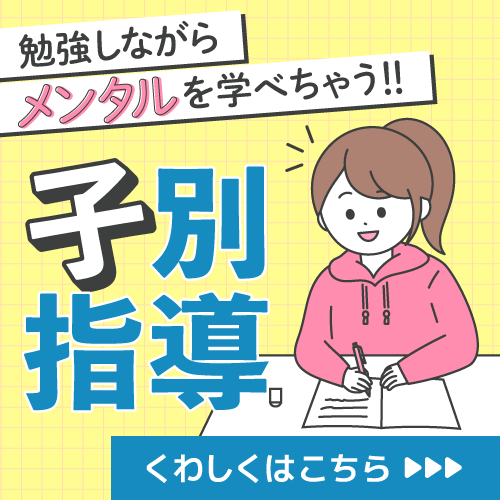子どもが学校に行けなくなったとき、
親として何ができるのか。
どうすれば笑顔を取り戻してくれるのか。
日々悩み、手探りで接しながら、
ふと「このままでいいのだろうか」と不安になることもあるでしょう。
そんな悩みを抱える方にとって、
“動物”という存在が新たな可能性を開いてくれることがあります。
人間関係に傷ついた心を、言葉ではない方法で癒してくれる存在
──それが、動物たちです。
筆者自身、以前「元不登校の会」を立ち上げ、
ともに活動していた仲間の中にも
「あの頃の私を愛犬が癒してくれた」と語っていた方がいました。
「学校に行けなかった日々、誰とも話したくなかったけれど、
犬だけは静かにそばにいてくれた。
あの存在があったから、自分を責めずにいられた」
──そう、しみじみ話してくれました。
その言葉には、深い実感と、
確かな手応えが込められていました。
私自身も、犬(ラブラドール)との暮らしの中で癒された一人です。
特に、朝夕の散歩は、ただの運動ではなく、
心のリズムを整える貴重な時間となっていました。
ラブラドールは成長が早く、毎日目に見えて体も心も大きくなっていく。
「昨日よりも少し遠くまで歩けたね」「こんな表情もするんだ」
──そんな発見が、沈んだ気持ちに小さな光を灯してくれました。
犬と一緒に過ごす日々が、
次第に「また明日も散歩に行こう」「あの子のためにごはんを作ってあげよう」と、
前向きな気持ちを生み出してくれたのです。

不登校を経験した子どもたちには、
ある“共通点”があると感じています。
それは、
将来に活かせる大きな可能性を秘めているということ。
私自身が元・不登校だったことに加え、
16年間多くの不登校の子どもたちを見守ってきた経験から、
本当に伝えたいことを無料のメール講座にまとめました。
気になる方は、ぜひ以下↓↓↓のリンクか画像からご覧ください。
不登校の時に犬を飼うことで生まれるアニマルセラピー的な変化
アニマルセラピーという言葉をご存じでしょうか?
これは、動物とのふれあいを通じて、
人の心や体の状態を和らげ、回復を促すケアの方法です。
不登校や引きこもり状態にある子どもたちは、
心を閉ざしてしまいがちです。
人との関わりに疲れ、
自己否定に陥ることも少なくありません。
しかし、犬は無条件に寄り添い、否定することなく、
ただそこに居てくれます。
それが子どもの心の扉を静かに、
けれど確かに開いていくのです。
不登校の子にとって犬の散歩が“外に出るきっかけ”になることも
犬を飼うことで生活には責任が生まれます。
毎日ごはんをあげたり、トイレを掃除したり、世話をする中で
「自分がやらなければ」という意識が自然と芽生えます。
中でも「散歩」は、犬にとっても飼い主にとっても、
心と体の健康を支える大切な日課です。
不登校だった子どもが、まずは「犬のために外に出る」
──それは決して大きなことではないように見えても、
実はとても意味のある一歩です。
最初はほんの5分でも、次第に10分、15分と時間が延び、
歩く距離も広がっていきます。
やがて季節の移ろいや空の色に気づいたり、近所の人に挨拶を返したりと、
小さな社会との接点が生まれていきます。
自然の空気に触れ、鳥の声を聞き、風に吹かれる
──そうした感覚が、張りつめた心をゆるやかにほどき、
静かに元気を与えてくれるのです。

世話をする”ことが自己肯定感につながる
犬の食事を用意したり、ブラッシングをしたりといった世話を通じて、
子どもは「役割」を担います。
それは「自分が誰かの役に立っている」という実感につながります。
毎日のお世話は、単なる義務ではありません。
「今日もあの子が待ってる」「この子の命を守るのは私だ」
という思いが、自然と心に根付きます。
そして、たとえうまくできない日があったとしても大丈夫です。
犬は怒ることなく、責めることもありません。
ただ静かに寄り添い、優しいまなざしで見守ってくれます。
その無言の信頼こそが、子どもにとって何よりの支えになります。
「失敗しても大丈夫」「自分は必要とされている」
──そんな感覚が、傷ついた心に少しずつ自信と安心を取り戻させてくれるのです。

ハムスターなど小動物でも効果あり
「犬はハードルが高い」「マンションで飼えない」という方には、
ハムスターやインコ、モルモット、ウサギなどの小動物もおすすめです。
実際に「うちはインコを飼っています。
朝、声をかけると返事をしてくれるのが嬉しくて、
子どもが自分から話しかけるようになった」
というお話もありました。
小さな命を守り、毎日お世話をするという行動の中には、
犬と同じように責任と喜びが伴います。
食事の準備、ケージの掃除、体調管理
──どれも簡単ではありませんが、
やればやるほど「自分がこの子を育てている」という実感が湧いてきます。
「生き物と暮らす」という体験そのものが、
子どもの心に優しさや達成感、そして生きる意味を与えてくれるのです。
不登校を経験した子どもたちには、
ある“共通点”があると感じています。
それは、
将来に活かせる大きな可能性を秘めているということ。
私自身が元・不登校だったことに加え、
16年間多くの不登校の子どもたちを見守ってきた経験から、
本当に伝えたいことを無料のメール講座にまとめました。
気になる方は、ぜひ以下↓↓↓のリンクか画像からご覧ください。
まとめ:犬を飼うことは“魔法”ではない。でも、希望のきっかけになる
もちろん、犬やハムスターを飼ったからといって、
不登校がすぐに解決するわけではありません。
それでも、子どもの中に「少しだけ笑う」
「少しだけ外に出る」という変化が見られたら、
それは大きな一歩です。
動物たちは、
そんな変化の“きっかけ”をくれる存在だと私は信じています。
子どもと一緒に過ごす時間が、
少しでも穏やかで温かいものでありますように。
✅ 記事のまとめポイント(要点)
-
動物は言葉のいらない癒し手
不登校で心を閉ざした子どもにも、動物はそっと寄り添い、安心感を与えてくれる。 -
犬との暮らしが生活リズムを整える
散歩やお世話を通して、昼夜逆転や無気力な生活に少しずつ変化が生まれる。 -
「犬のために外に出る」が第一歩
無理に学校に行かせるのではなく、犬の散歩が自然な形で外出の習慣につながる。 -
責任感と役割意識が芽生える
ごはんやブラッシングなどの世話を通じて「自分が必要とされている」と実感できる。 -
失敗しても責められない安心感
犬や動物は怒らず、見守ってくれる存在。自己否定の強い子どもにも心の余裕が生まれる。 -
成長していくペットの姿が励みになる
特にラブラドールのように日々変化が見える動物は、「一緒に進んでいる」感覚を持たせてくれる。 -
犬以外の動物でも効果はある
ハムスター、インコ、ウサギなどの小動物も、不登校の子どもにとって良いパートナーとなる。 -
「命を預かる」という体験が心を育てる
生き物と向き合う中で、共感力や忍耐力、優しさが育まれていく。 -
動物とのふれあいは親子関係にも良い影響
「今日はインコに話しかけてたよ」「一緒に散歩行けたね」など、会話のきっかけが増える。 -
アニマルセラピーの考え方が現実的な支えに
特別な療法ではなく、家庭でできる自然な関わりが、心の回復に役立つ。 -
動物は“解決策”ではなく“きっかけ”
魔法のように問題が消えるわけではないが、前向きな変化の入口になり得る。 -
親もまた癒される存在
不登校に悩む親自身も、ペットと接することで気持ちがほぐれる瞬間を得られる。
この記事を読んでいる人はこちらの記事も読んでいます
N中等部はいじめがあるかを生徒に聞いてみた
【2025年版】高3で不登校から大学受験へ|間に合うために今やるべきこと
N高等学校の進学実績はなぜ高い?理由をわかりやすく解説
不登校と罪悪感──子どもと親、それぞれの心を軽くするために
中高一貫校での不登校に負けない:復学と進路の実例紹介
なぜ芸能人に不登校経験者が多いのか⁉その理由を徹底解説