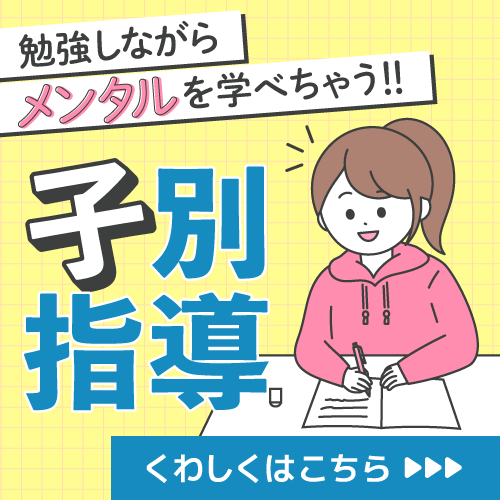今、私たちが生きている社会では、
「学校に行くのが当たり前」「毎日登校するのが当然」という価値観が、
ごくごく自然なものとして広まっています。
ニュースやメディア、周囲の大人たちの言葉の端々にも、
無意識のうちにそのメッセージは含まれていて、
子どもたちは小さなころからそれを受け取っています。
そのため、ほんの一日でも学校を休むと、
子どもは「自分は普通じゃないのかもしれない」「周りに迷惑をかけているかもしれない」と、
心の奥で静かに、しかし確かに罪悪感を抱えてしまうことが少なくありません。
それは誰かに責められたわけではなくても、
自分で自分を責めてしまうような、そんな苦しさを生み出します。
そして、その子どもの様子を間近で見ている親もまた、
「もしかして自分の育て方が悪かったのではないか」
「もっと違うサポートができていれば…」と、
理由のわからない罪悪感にとらわれることがあります。
愛情が深いからこそ、どうしても自分を責めてしまう
――それは親にとっても、とてもつらいことです。
この記事では、「子どもの罪悪感」「親の罪悪感」をそれぞれ分けて丁寧にひもときながら、
どうすれば少しでも心が軽くなり、前を向いて歩んでいけるのか、
一緒に考えていきたいと思います。
不登校を経験した子どもたちには、
ある“共通点”があると感じています。
それは、
将来に活かせる大きな可能性を秘めているということ。
私自身が元・不登校だったことに加え、
16年間多くの不登校の子どもたちを見守ってきた経験から、
本当に伝えたいことを無料のメール講座にまとめました。
気になる方は、ぜひ以下↓↓↓のリンクか画像からご覧ください。
不登校の子どもが感じる罪悪感
なぜ学校を休むと罪悪感を感じるのか?
学校に行くのが当たり前、
という社会的メッセージが当たり前になっています。
このため:
-
親や兄弟姉弟の期待
-
先生からの目
-
友達に必要以上に気を使う
これらが重なり、
「自分は誤ったことをしている」「ひどい人間だ」と思いこんでしまうのです。
一方、罪悪感がなさそうに見える子もいる
一部の子は、
家で元気にゲームやテレビを楽しんでいるように見えることもあります。
しかし、これは「一時的な自衛」「つかの間の忘却」である場合も多く、
深い所にはやはり罪悪感や思い込みが隠れていることも少なくありません。
引きこもりに致ることもある
罪悪感が大きすぎると:
-
自己否定が進む
-
世界と切れてしまう
-
外に出る気力もなくなる
この結果、いわゆる「引きこもり」状態になることも現実にあります。

不登校の子どもの罪悪感へのケアポイント
まず大切なのは、子どもが感じている罪悪感を無理に否定しないことです。
「そんなふうに思わなくていいよ」と励ましたくなる気持ちもあるかもしれませんが、
罪悪感を抱くこと自体が、その子の真面目さや優しさの表れでもあります。
だからこそ、「そんなふうに思ってしまうよね」「それだけ周りを大切に思っているんだよね」と、まずは子どもの気持ちに寄り添ってあげることが大切です。
そして、ほんの小さなことでいいので、「できた」「やれた」という成功体験を少しずつ積み重ねていきましょう。
たとえば、朝決まった時間に起きられた、家族と笑って話せた、好きなことに集中できた――そんな一見ささやかなことも、心の回復には大きな意味を持ちます。
「やれたこと」に目を向け、少しずつ自己肯定感を取り戻していけるようサポートしていきます。
また、子どもが自分自身を責めなくてすむような環境を整えることも、欠かせないポイントです。
「学校に行かない自分はダメだ」ではなく、
「今は休む時間なんだ」「元気になるために必要なステップなんだ」と感じられる空気を、
家の中に作っていきたいものです。
これらの取り組みが、子どもが抱えている罪悪感を少しずつ減らし、
そして、心を落ち着かせ、再び前を向く力を取り戻していくために、
確かな支えになっていきます。
不登校の子の親が感じる罪悪感
なぜ親も罪悪感を抱くのか?
-
「自分の育て方が悪かったのでは」
-
「誰とは言わないけれど社会に面目なのでは」
-
結果として小さい事で自分をせめる
この程度は人によりますが、
親として子を思うがゆえの自然な感情でもあります。
親の罪悪感が悪化すると
-
子どもへの焦りが増してプレッシャーになる
-
自分を小さく見るようになり、心が疲弊する
結果、親子ともに気力が下がってしまい、長期戦になりやすくなります。

親御さんのセルフケアのポイント
まず知っておいてほしいのは、「不登校は誰にでも起こりうる」ということです。
どんなに愛情をかけて育てても、どんなに気を配っていても、
環境やタイミング、本人の繊細な感受性など、
さまざまな要素が重なって、不登校は起こることがあります。
それは決して、親のせいではありません。
「こうしていれば防げたはず」と過去を悔やむよりも、
「これからできること」を一緒に見つけていくことが大切です。
また、自分を罪めない努力を意識してみてください。
自分を責めることがクセになってしまうと、
エネルギーがどんどん削られてしまいます。
もちろん、最初からポジティブに考えられる必要はありません。
「そんなふうに思ってしまうくらい、私はこの子を大切に思っているんだな」と、
自分の気持ちに優しく寄り添うことから始めてみましょう。
さらに、カウンセリングや支援機関など、外からのサポートを受け入れることも、
とても有効な手段です。
「自分だけで何とかしなければ」と抱え込まずに、
誰かの手を借りることは、親として弱いわけでも、無責任でもありません。
むしろ、それは「本当に子どもを大切に思っているからこそ」できる行動です。
子どもを支えるためには、親自身がまず元気でいること。
親の心が安定していれば、きっとそのあたたかさは、
自然と子どもにも伝わっていきます。
だからこそ、まずは自分自身を大切にしてあげてくださいね。
不登校を経験した子どもたちには、
ある“共通点”があると感じています。
それは、
将来に活かせる大きな可能性を秘めているということ。
私自身が元・不登校だったことに加え、
16年間多くの不登校の子どもたちを見守ってきた経験から、
本当に伝えたいことを無料のメール講座にまとめました。
気になる方は、ぜひ以下↓↓↓のリンクか画像からご覧ください。
まとめ:不登校の罪悪感とうまく付き合うために
罪悪感を抱いてしまうこと自体は、決して悪いことではありません。
むしろそれは、子どもも親も、
それだけ真剣に向き合っている証でもあります。
でも「学校に行けない自分はダメだ」とか、
「子どもを不登校にしてしまった自分は失格だ」などと、責める必要はないのです。
その罪悪感をずっと心の中に持ち続ける必要もありません。
罪悪感は、そっと抱いて、そして少しずつ手放していくものです。
大切なのは、子どもも親も、「一気に解決しよう」と焦るのではなく、
「少しずつ、楽になっていくこと」を目指すこと。
昨日より今日、今日より明日、
ほんの少しでも心が軽くなれば、それで十分です。
たとえ回復までに時間がかかったとしても、
たとえ周りと比べて遠回りに見えたとしても、
それぞれが自分のペースで、
罪悪感を少しずつ手放しながら、前に進んでいけば大丈夫。
ゆっくりでも、一歩一歩、その道のりはちゃんと力になっていきます。
あなたも、あなたの子どもも、今この瞬間を生きているだけで、
十分に頑張っているのですから。
【この記事のまとめポイント】
-
子どもは学校を休むだけで無意識に罪悪感を抱きやすい
-
親もまた、子どもの不登校をきっかけに自分を責め、罪悪感を抱くことがある
-
子どもの罪悪感は、本人の真面目さや優しさの表れでもある
-
罪悪感を無理に否定せず、「感じるのは自然なこと」と寄り添うことが大切
-
小さな成功体験を積み重ねることで、子どもは少しずつ自己肯定感を取り戻せる
-
「いけない自分」を責める雰囲気を作らず、安心できる家庭環境を整えることが重要
-
親も「不登校は誰にでも起こりうる」と理解し、自分を過剰に責めない努力が必要
-
親自身の心のケアのために、支援機関やカウンセリングの利用も選択肢に入れる
-
子どもを支えるには、親自身が元気であることが何より大切
-
罪悪感は悪いものではないが、持ち続ける必要はない
-
子どもも親も「すこしずつ楽になる」ことを目標にする
-
たとえ時間がかかっても、自分のペースで歩んでいけば大丈夫
-
今できることを一歩ずつ積み重ねることが、回復への確かな道となる
中高一貫校での不登校に負けない:復学と進路の実例紹介
なぜ芸能人に不登校経験者が多いのか⁉その理由を徹底解説
「なんでうちの子が」不登校になる子ならない子について解説します
経験者が語る不登校経験者にしかわからない深い心の声10選
N中等部はいじめがあるかを生徒に聞いてみた
不登校対応、担任はめんどくさいと感じているのか?実際の先生に聞いてみた